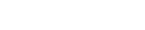以前、退職者のメールアカウントの取り扱いについてコラムを書かせていただいたことがありますが、今回はその続編として、実際に社内で起こり得る事例を2つご紹介します。いずれも「よくあること」「誰でもやってしまいがちなこと」ですが、放置すると思わぬトラブルに発展する可能性があります。
≫ 退職社員のメールアドレスでトラブルやビジネスチャンスを逃してませんか?
廃止アドレス宛に一斉配信が続いて他のメンバーにエラーメールが届く問題
「Aさんは退職したけど、とりあえずメーリングリストはそのままでいいか」と思っていたら、その判断が後々面倒を引き起こすことがあります。
たとえば、退職したAさんのメールアドレスが含まれたままの一斉送信メールを継続して送っていると、Aさん宛のメールは当然「配信不能」となり、エラーメール(いわゆるリターンメール)が送信元に返ってきます。
ところが、この「返ってくる先」が必ずしも送信者本人とは限らず、CCに入っていた別の社員に届いたり、グループメールを経由して意外な人が受け取ったりすることがあります。
「毎回知らない英語のエラーメールが届いてうっとうしい」
「このエラーは自分のせい?」
といった混乱が社内で広がる原因にもなります。
対応のポイントはシンプルです。退職者が出たら、メーリングリストや配信グループの見直しをセットで行う。
これだけで未然に防げる問題です。地味ながらも社内の情報流通を円滑に保つためには大切な習慣と言えるでしょう。
廃止メールアカウントがPCに設定されたままのまま、新社員が同じPCを使った場合
こちらは少し特殊なケースですが、実際に報告されている例です。
たとえば、退職者のメールアカウントが設定されたままのパソコンに、新しく入社した社員が自分のメールアカウントを追加して使用したとします。すると、メールソフトは「残っている廃止済みのアカウント」にもアクセスを試みてしまい、ログインエラーを何度も繰り返します。
この状態が続くと、メールサーバ側では「不正アクセスが繰り返されている」と認識されてしまい、社内のIPアドレス全体が“攻撃元”とみなされて、プロバイダ側でメール送信機能が一時的に停止されてしまうことも。
突然「会社全体でメールが送れない!」という事態に陥る可能性があるわけです。
このトラブルを防ぐには、退職時にメールアカウントだけでなく、その設定を含めた端末環境のリセットが重要です。IT部門だけでなく、各部署でも「アカウント削除がされているか?」の意識を持っておくことが安全管理の第一歩になります。
メールアカウントは「見えない名刺」とも言える重要な情報資産です。退職者のアカウントをどう扱うかは、情報漏えいや業務トラブルの防止にも直結します。
ちょっとした点検と見直しが、会社全体の情報セキュリティを守る大きな力になります。